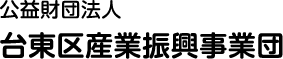【参加者】23名(内入学前のお子さん5名)
今回はテレビでも度々紹介されている、日本随一の技術を誇る伝統飴細工専門店の浅草 アメシン 花川戸店で「飴細工」の体験教室です。お題は「うさぎ」、さてどんな「うさぎ」が出来上がるのでしょうか…




前回の「雷おこし」そして前々回の「そば打ち」でセンスのなさを思い知ったので、今回は体験ではなく見学に。今回の「飴細工」は大変人気があり、狭き門を突破した18名の方が体験教室に参加。お子さんとご一緒にの参加も多く、入学前のお子さんも5名(保護者とご一緒の未就学のお子さんお1人は無料です)。
体験教室の流れは①ビジュアルによるハサミの使い方、うさぎの作り方の説明、②アメシンの講師の方のデモンストレーション、③練習を2回、④本番となります。
うさぎの作り方ですが、90℃ほどに熱した飴を丸め(講師の方が2本の棒を使って手際よく丸めます)、70℃(体感的には熱いお湯の入った湯のみじゃわんを触った感じ)くらいになったところで、棒の先端で丸くなっている飴をハサミと指を使いうさぎに仕上げていきます。
まずは、耳から。飴はまだ熱く、また直接手で触れると形が崩れますので、作業はすべて棒に付いたままで行います。丸い飴から大まかですが、頭と胴体がわかる形で手渡されますので、頭の部分に素早くハサミを入れ、指で立てて、伸ばしたり丸みを付けたりで、耳にします。耳に限らず、飴は時間とともにどんどん固まっていきますので、作業は素早く。一方で、まだ柔らかいので力を入れすぎると形が崩れるので優しくと、何とも微妙なさじ加減が飴細工には必要なようで、このあたりが人気のヒミツかと。
耳の次は、前足、後ろ足、尻尾と作業が進みます。本番前に練習が2回あり、講師の方も適宜アドバイス。無言で真剣にハサミを入れる瞬間もあれば、「耳もう少し伸ばしたした方が良いんじゃない?」「お母さん、足曲げすぎ!」などの楽し気な会話も聞こえてきます。
2回の練習が終わるといよいよ本番。みなさん気合が入ります。熱した飴は透明ですが、2本の棒で手早くねじって丸めていく内に空気が入り、うさぎのように白くなっていきます。(練習用の飴は茶色です)練習の成果ありで、作業もどんどん進みオンリーワンのうさぎが次々と出来上がっていきます。
そして、ここからは練習にはなかったこと。食紅で目と口を書きます。二つの点と僅かな線を入れただけで表情が出てきます。「うさぎ」から「うさぎさん」になった感じです。
オンリーワンのうさぎさんは、もちろんお持ち帰りですが、その前に撮影タイム。背景用にパネルも何種類か用意されおり、袋詰めの前に皆さんスマホでパッチリ。
飴は温度より湿度に弱いそうで、5月から10月は要注意。賞味期限は1年ですが、食べてしまうのは…?の方には、保存が良ければ数年は形が崩れないそうです。
ということで、ケースをお買求めの方も。
11時から始まって13時に終了。参加された皆さんにとって、とても楽しい2時間だったようです。
2024年2月24日(土)に開催しました。
会 場:雷5656会館(台東区浅草3丁目)
参加人数:15名
講 師:5656会館スタッフの皆さん
【体験レポート】
雷おこしの体験ということで15名の参加者のうち、お子さんが8名と半数以上。お子さんは保護者同伴なので総数は23名。
会場は5656会館の2階の売店奥に体験スペースがあり、今回の11時からの部は、参加者15名以上いるので貸切に。
体験では、自分好みのおこしを作れるということで、おこし種を「お米」か「小麦」、味は「砂糖」か「キャラメル」から選択することができ、スタッフの方が参加者1人1人に注文を聞いて回ります。
(参加者ファーストで、好印象ですね。)

注文の結果は体験スペース内にある調理台に反映され、1人1人名前が呼ばれ指定された調理台に。
自分は「お米」と「砂糖」を選択したので、目の前の調理台には「お米」と「砂糖」、それに「ピーナッツ」と調理器の上には「水飴」が入った鍋。その他には『おこし』を入れるパットと『おこし』伸ばす棒状のもの(名前は?)、それに『おこし』を裁断するための「裁断枠」と「カッター」。さらにできた『おこし』を持ち帰るための「オリジナル缶」が並ぶ。
まずはスタッフの方のデモンストレーション。
水飴が入った鍋を200℃で沸騰させ「砂糖」(または「キャラメル」)を入れ木ベラでかき混ぜ、そこに「ピーナツ」を入れ、温度を20℃下げ、さらにかき混ぜる。
ここでかき混ぜることを怠ると鍋が焦げる。
木ベラを持ち上げ糸を引くようになったら(糸は3本が目安)、温度を20℃下げ、おこし種を入れ素早くかき混ぜる。
よく混ざったら、『おこし』を正方形のパットに移し、素早く形に伸ばし、伸ばし終えたら裁断枠を上に乗せ、ひっくり返す。
ひっくり返すと『おこし』は裁断枠に移動しているので、移動した『おこし』をカッターで裁断し終了。
この間10分程度。要は始まったら素早くやって下さい、と言うことのようです。
それでは、スタート。
「砂糖」を大ぶりのスプーンで一杯だけすくい(量はお好みですが一杯が普通のようです。)かき混ぜ「ピーナツ」を入れる。
「水飴」に「砂糖」を加え煮ているので、すぐに粘着力が出てきたので、おこし種を入れる。
入れた途端、重い。とにかく重く中々混ざらない。そして鍋にくっ付いてきた。
これ以上鍋に留まると焦げそうなので、パットに移し伸ばす。
自分は不器用だと言われているが、確かにそのようで、正方形のパットの中で伸ばせば正方形になるはずなのに、四隅が欠けている。

さらに不器用な証明の第2弾は、カッターで裁断すると切れ目が付き、その切れ目に沿って両手でパッチンすれば、綺麗な直方体の『おこし』ができるはずだが、切れ目が上手く付かず、いびつな『おこし』が…。
でもお味は「最高!!」。
当たり前だが、今まで温かい『おこし』は食べたことがないが、これがまた実に美味しい。

出来上がった『おこし』は、「オリジナル缶」に詰めてお持ち帰り。
で、これで終わらず、最後は家庭で作れる2回分の「手作りおこしキット(おこし種、ピーナツ、水飴)」がお土産に。

同じフロア―が売店なので、おこしをお土産に買って帰る参加者の姿も…。
さて、お土産のおこしキット。
どうアレンジして使うか。楽しみは終わったあとも続くのでした。
2023年2月25日(土)に開催しました。
会 場:全麺協研修センター(台東区西浅草2丁目)
参加人数:午前の部 8名、午後の部 8名の計16名
講 師:全麺協の会員の皆さん 8名、延べ16名
【体験レポート】
自分は初めての経験で不安でしたが、そこはマンツーマン指導なので、最後は美味しくいただくことができました。
参加者1人に対して講師の方が1名、そば打ち台が1台と恵まれた環境の中、教室がスタート。

最初はそば粉と小麦粉を混ぜ、水を加えそば生地を作っていくのですが、これが結構難しく、粉に万遍なく水を吸わせることができず、むらが出て上手く行きません。こうなると講師の方の出番です。何とも素晴らしい手さばきで、耳たぶくらいの柔らかさになった粒が数多く出来上がって行きます。

次は、コシを出すために生地をこねるのですが、腕の力ではなく体重を掛けて…と言われても、どうしても腕の力に頼ってしまう自分が悲しい。😢😢
生地から空気を抜く煉り方を「菊練り」と言い、丸まって行くと中心部が菊の花のような形となるのですが、講師は方は菊の花ですが、自分はどう見ても菊の花ではない。
次は、まん丸になった生地を細長いそばとするために、薄い四角形に形を整えていく作業です。

最初は両手で丸く伸ばしていき、その後は麺棒の登場です。丸いものを四角にするのには?まずは菱形にして角を出していきます。対角線上に角が出たら、次に反対側の角を出し、あとは均等の厚さに伸ばしていきます…と簡単に書いていますが、実際には均等の厚さでもないし、四角形でもないし。こうなると講師の方の出番です。
さて、そば打ちも最終行程に来ました。

いよいよそば切包丁でそばを切る作業です。自分が切ると、細くなったり太くなったりだろうなという予感でしたが…大当たり。
でも何事にも「コツ」はあるもので、「コツ」を講師の方から伝授され、最後はどうにか均等に良い感じ終了。
この間1時間30分ほどでしたが、あっという間に時間が過ぎました。
その後はお楽しみの試食タイム。

そば打ちは各自でしたが、試食は参加者一同が同じテーブルにつき、皆さんで楽しく自分の打ったそばをいただきました。
さて、お味の方はと言うと。もちろん「最高」‼
でこれで終わりではなく、500gの粉+水を含んでいますので、試食だけでは食べきれず、残りは持ち帰りとなります。
当然夕食はそば。美味しいそばを食べられ、家族にも喜ばれで、言うことなし。
翌日もそばでしたが、自分の打ったそば何気に飽きない。(^_-)